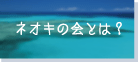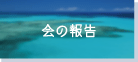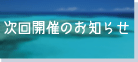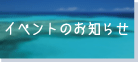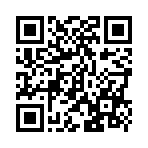2008年10月28日
【報告】泡瀬干潟観察会
南西諸島最大の干潟といわれる沖縄市の泡瀬干潟。
ここを埋め立てて人工島を造り、ホテルや企業誘致を目指す国と県との事業に対して、長年にわたり根強い反対運動が続けられています。
事業を推進する側が主に「経済効果」を期待し、事業中止を求めている人たちが主に「環境破壊」を懸念していることは、新聞やテレビの報道でも伝わってきます。
でも、そもそも泡瀬干潟ってどんなところ?
そう聞かれて答えられる人は少ないのではないでしょうか。
そこで、まずは現地を見てみようということで、ネオキの会の泡瀬干潟ツアーが10月26日、開催されました。
参加者は子どもも含めて総勢15人ほど。
案内してくださったのは、「泡瀬干潟を守る連絡会」の屋良朝敏さんと水野隆夫さん。沖縄野鳥の会の吉里伸さんも同行してくださいました。
出発地点は、米軍泡瀬通信施設脇の海岸。
中潮の干潮時で、数百メートル沖合まで干潟が広がっていました。
その先で、埋め立て現場が水平線を隠しています。
日曜でしたが、クレーンやパワーショベルなどの工事車両が音を立てて作業をしていました。
一期工事の完成した護岸の内側で埋め立てが進んでいます。
「来年1月には一番大事なサンゴがある海域の埋め立てが始まる」と水野さんはいいます。

まず岸から望遠鏡で野鳥の観察。くちばしの長いダイシャクシギが砂の中からエサをつつき出している様子が見えました。
吉里さんによると、環境悪化で漫湖(那覇市)への渡り鳥の飛来が激減する一方、泡瀬干潟への飛来が増え、今では県内でも一、二を争う水鳥の飛来地となっているそうです。
中でも、胸の黒さが特徴のムナグロは、全国の50%が泡瀬で越冬するともいわれ、日本最大の越冬地ではないかといいます。
コアジサシやシロチドリが繁殖する砂洲もすぐ近くだそうです。

干潟に下りてゆくと、様々な種類の貝殻やサンゴのかけらが目につきます。



泡瀬の埋め立て事業は元々、中城湾港の新港地区開発のため浚渫土砂の捨て場として計画されたもので、干潟49ヘクタールを含む約187ヘクタールを埋め立てて人工島を造り、2011年ごろの使用開始を目標にホテルやマリーナ、人工ビーチなどを建設するというものです。
事業主体は国(約178ヘクタール分)と沖縄県(約9・2ヘクタール分)で、総事業費は約650億円にのぼります。沖縄市にも造成後に土地利用の費用負担が生じます。
現在は、計画全体の約半分に当たる第一期工事(約96ヘクタール)の埋め立てが進んでいる段階まできています。
事業者は、埋め立てで潰れる干潟は全体の2割に過ぎないと強調していますが、「守る連絡会」の側では、海流や水質の変化によって残された干潟にも大きな影響が出るだろうと指摘しています。
今回のツアーでは、埋め立ての公共事業としての妥当性や手続きの適正性、「経済効果」とされるものが実際にどの程度見込めるのかなどの検討にまでは至らず、ただ現場を見ただけでした。それでも、いろいろ考えさせられたことはあります。

遠くから見た限りでは、一面の泥か砂にしか見えなかった干潟ですが、実際に歩いてみると、砂礫地や泥地、粗い砂地、細かい砂地、砂洲など様々な顔がありました。砂にも白っぽい砂や黒っぽい砂など変化があります。
海底地形の複雑さが土質の多様性を生み、多様な種類の生物の生存を可能にしているのだといいます。
屋良さんによると、泡瀬干潟では鳥類や植物なども含めると1000種もの生き物が暮らしているそうで、まさに「生物多様性の宝庫」といえます。
けれど、干潟には観光ガイドブックに載っているサンゴ礁の写真のような「華やかさ」はありません(もっとも、埋立予定地の浅瀬には貴重なサンゴの群落が含まれていますが)。
干潟の地味な豊かさが多くの人に実感を伴って知られなければ、生産性を欠いた無価値な場所だから埋めて「有効利用」すればいいだろう、という発想が力を持つだろうことは想像に難くありません。
地味でかつ大切なものを、それにふさわしい重さで自分の中に価値づける感性は、私たちにどれだけ残っているのでしょうか。

タコ獲りの様子などを眺めていると、昔から人々が干潟に親しみ、生活のたつきともして暮らしてきたんだろうなということを考えます。
同時に、無数の生と死が濃密に絡み合う干潟は、生命の発祥にまで遡る仄暗さを感じさせもします。安心感とも懐かしさとも呼べるような感覚です。
水野さんは「ここに来ると鬱病でさえ治ってしまう。泡瀬干潟は総合病院であり、博物館であり、美術館だ」と話していましたが、たしかに「癒し」としか言いようのない作用があるように思います。
一方で水野さんは、「干潟なんか早くなくして、人工島にできる人工ビーチで子どもを遊ばせたい」という住民の声があると言って、嘆いてもいました。「遊ばせたいなら、まず干潟に来たらいいのに」と。
私たちの暮らしぶりは日々、いろいろな点で倒錯していますが、本当に大切なものは何かということを常にとらえ返して、生活の軌道を修正していく習慣をつけたいものだと思います。



報告 : ネオキの会 佐藤拓
ここを埋め立てて人工島を造り、ホテルや企業誘致を目指す国と県との事業に対して、長年にわたり根強い反対運動が続けられています。
事業を推進する側が主に「経済効果」を期待し、事業中止を求めている人たちが主に「環境破壊」を懸念していることは、新聞やテレビの報道でも伝わってきます。
でも、そもそも泡瀬干潟ってどんなところ?
そう聞かれて答えられる人は少ないのではないでしょうか。
そこで、まずは現地を見てみようということで、ネオキの会の泡瀬干潟ツアーが10月26日、開催されました。
参加者は子どもも含めて総勢15人ほど。
案内してくださったのは、「泡瀬干潟を守る連絡会」の屋良朝敏さんと水野隆夫さん。沖縄野鳥の会の吉里伸さんも同行してくださいました。
出発地点は、米軍泡瀬通信施設脇の海岸。
中潮の干潮時で、数百メートル沖合まで干潟が広がっていました。
その先で、埋め立て現場が水平線を隠しています。
日曜でしたが、クレーンやパワーショベルなどの工事車両が音を立てて作業をしていました。
一期工事の完成した護岸の内側で埋め立てが進んでいます。
「来年1月には一番大事なサンゴがある海域の埋め立てが始まる」と水野さんはいいます。
まず岸から望遠鏡で野鳥の観察。くちばしの長いダイシャクシギが砂の中からエサをつつき出している様子が見えました。
吉里さんによると、環境悪化で漫湖(那覇市)への渡り鳥の飛来が激減する一方、泡瀬干潟への飛来が増え、今では県内でも一、二を争う水鳥の飛来地となっているそうです。
中でも、胸の黒さが特徴のムナグロは、全国の50%が泡瀬で越冬するともいわれ、日本最大の越冬地ではないかといいます。
コアジサシやシロチドリが繁殖する砂洲もすぐ近くだそうです。
干潟に下りてゆくと、様々な種類の貝殻やサンゴのかけらが目につきます。
泡瀬の埋め立て事業は元々、中城湾港の新港地区開発のため浚渫土砂の捨て場として計画されたもので、干潟49ヘクタールを含む約187ヘクタールを埋め立てて人工島を造り、2011年ごろの使用開始を目標にホテルやマリーナ、人工ビーチなどを建設するというものです。
事業主体は国(約178ヘクタール分)と沖縄県(約9・2ヘクタール分)で、総事業費は約650億円にのぼります。沖縄市にも造成後に土地利用の費用負担が生じます。
現在は、計画全体の約半分に当たる第一期工事(約96ヘクタール)の埋め立てが進んでいる段階まできています。
事業者は、埋め立てで潰れる干潟は全体の2割に過ぎないと強調していますが、「守る連絡会」の側では、海流や水質の変化によって残された干潟にも大きな影響が出るだろうと指摘しています。
今回のツアーでは、埋め立ての公共事業としての妥当性や手続きの適正性、「経済効果」とされるものが実際にどの程度見込めるのかなどの検討にまでは至らず、ただ現場を見ただけでした。それでも、いろいろ考えさせられたことはあります。
遠くから見た限りでは、一面の泥か砂にしか見えなかった干潟ですが、実際に歩いてみると、砂礫地や泥地、粗い砂地、細かい砂地、砂洲など様々な顔がありました。砂にも白っぽい砂や黒っぽい砂など変化があります。
海底地形の複雑さが土質の多様性を生み、多様な種類の生物の生存を可能にしているのだといいます。
屋良さんによると、泡瀬干潟では鳥類や植物なども含めると1000種もの生き物が暮らしているそうで、まさに「生物多様性の宝庫」といえます。
けれど、干潟には観光ガイドブックに載っているサンゴ礁の写真のような「華やかさ」はありません(もっとも、埋立予定地の浅瀬には貴重なサンゴの群落が含まれていますが)。
干潟の地味な豊かさが多くの人に実感を伴って知られなければ、生産性を欠いた無価値な場所だから埋めて「有効利用」すればいいだろう、という発想が力を持つだろうことは想像に難くありません。
地味でかつ大切なものを、それにふさわしい重さで自分の中に価値づける感性は、私たちにどれだけ残っているのでしょうか。

タコ獲りの様子などを眺めていると、昔から人々が干潟に親しみ、生活のたつきともして暮らしてきたんだろうなということを考えます。
同時に、無数の生と死が濃密に絡み合う干潟は、生命の発祥にまで遡る仄暗さを感じさせもします。安心感とも懐かしさとも呼べるような感覚です。
水野さんは「ここに来ると鬱病でさえ治ってしまう。泡瀬干潟は総合病院であり、博物館であり、美術館だ」と話していましたが、たしかに「癒し」としか言いようのない作用があるように思います。
一方で水野さんは、「干潟なんか早くなくして、人工島にできる人工ビーチで子どもを遊ばせたい」という住民の声があると言って、嘆いてもいました。「遊ばせたいなら、まず干潟に来たらいいのに」と。
私たちの暮らしぶりは日々、いろいろな点で倒錯していますが、本当に大切なものは何かということを常にとらえ返して、生活の軌道を修正していく習慣をつけたいものだと思います。
報告 : ネオキの会 佐藤拓
Posted by ネオキの会 at 23:03│Comments(0)
│● 会の報告 ●
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |